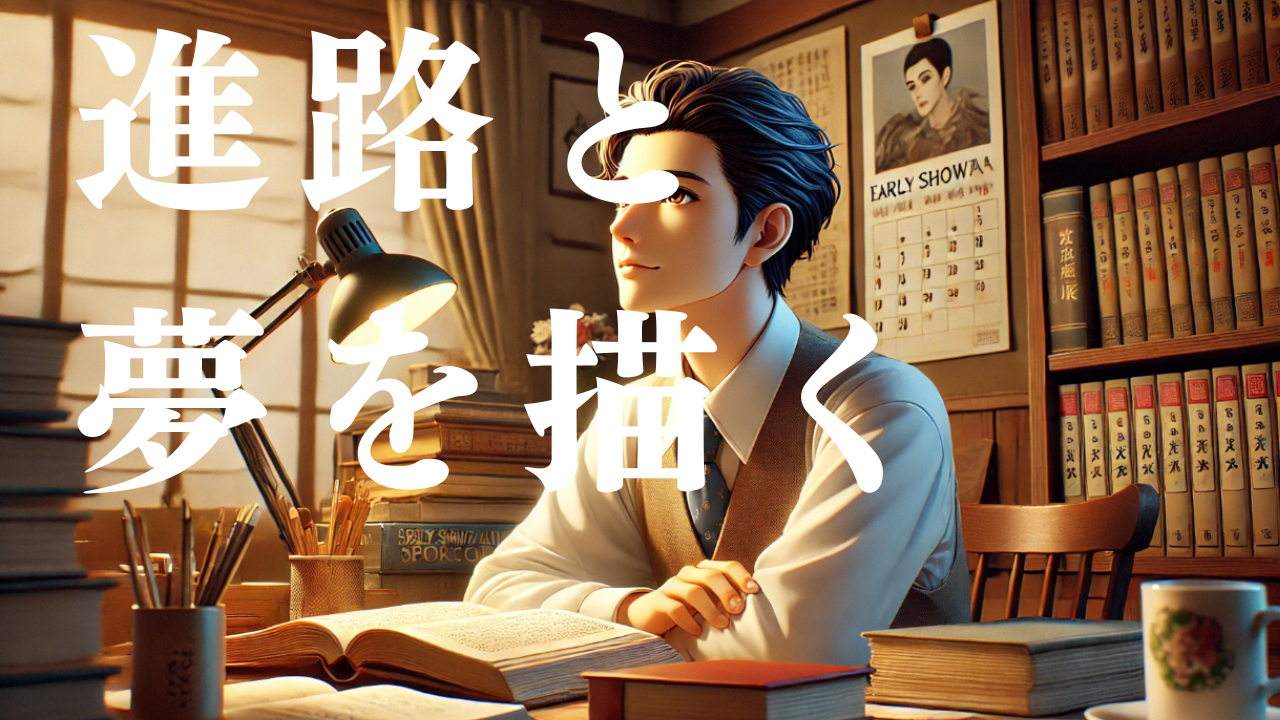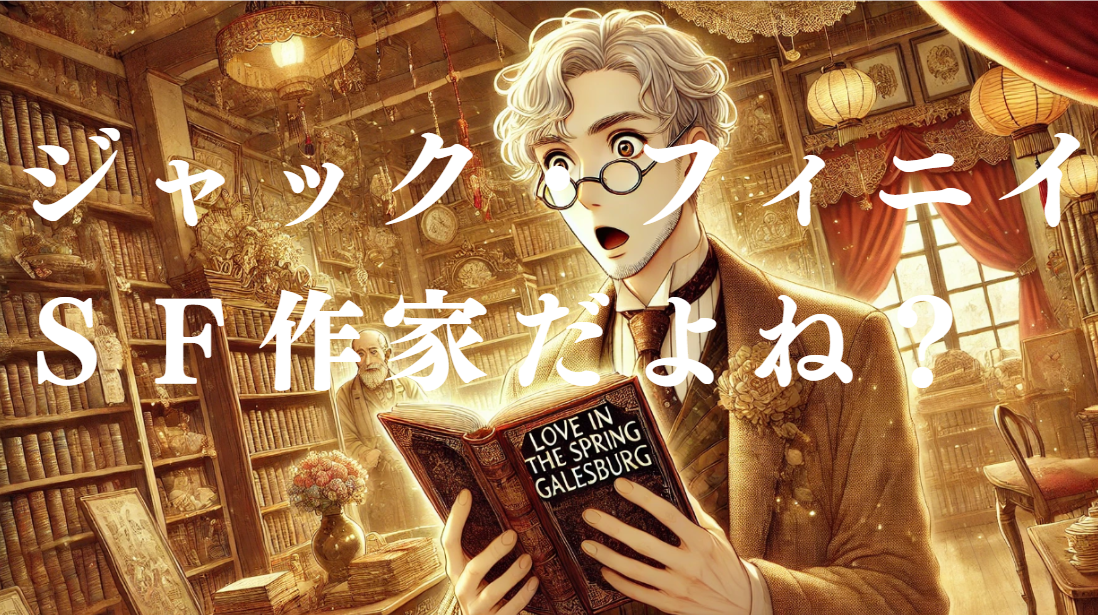進路と夢を描く
特に印象的な小説との出会いが起こるにはその人の人生におけるタイミングがあると思う。どんなに素晴らしい小説であっても、それが自分の状況や年齢等によって心に響く内容は違うはずだ。
サマセット・モームは読者への薦めとして『世界の十大小説』を書いている。そこにはドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』トルストイ『戦争と平和』エミリー・ブロンテ『嵐が丘』バルザック『ゴリオ爺さん』スタンダール『赤と黒』等、素晴らしい作品が紹介されている。僕自身もこれらのいくつかは読み、それなりの感動はあった。しかしそれらを手にした動機は何かはっきりしないものだった。つまりその時それを読む必然性のようなものはなく、偶然や気まぐれだったと思う。だからもし今、人にあなたの特に印象的な小説との出会いはなんですか? と問われたならば僕は即座にこう答える。
「それは、ロマン・ロランの『ジャン・クリストフ』です」と。残念ながらモームのお薦めの世界十大小説には入っていない。しかしその小説との出会いは僕にとって必然だったと今にして感じる。
もう五〇年以上前のことになる。僕が在籍していた高校は進学校だった。しかし、授業は面白くなくその日その日をただ消化しているような、何か青春を無駄にしているような日々を過ごしていた。もっとも現代国語の授業だけは少し面白く、その影響もあって当時いくつかの小説は読んだことがある。例えば武者小路実篤の『友情』夏目漱石『三四郎』等であるが、それらは軽いお茶を飲んだというような印象だった。自分自身もそんな軽いフワフワした、自分がどのような人間になりたいのか、何に憧れどう生きたいのかをつかめない高校生活を送っていた。ただ単純に大学に行くのだと思っていた。そして所属していたトレーニング重視の卓球部で、毎日ランニングをし、体力を使い果たしていた。苦しかった。
高三になった春、友人達と大学はどこへ行くのかという話をし、僕も志望する大学を探し始めたそんな時だった。突然、滅多に会うことのない和歌山の叔父がやって来た。彼は何か重い雰囲気を持って僕を自分の前に座らせた。そして、話し始めた。
「いいか、よく聞け。どうやらお前は大学進学を考えているようだが、それはならん。お前は母親を助け自分で生きていけるように、高校を卒業したらすぐ就職するんだ。お前の希望とは違うだろうが、父親が亡くなり、母子家庭のお前を大学にやるような余裕は母さんにはない。それが現実というものだ」
というようなことを厳に言って、帰って行った。おそらく母はそのことを直接僕に言うことが辛くて、叔父に頼んだのだろう。その時はじめて僕は自分の現実を知った。今から思えばそれは当然のことであったと思うけれど。当時の僕の高校では男子生徒が就職した例は一件もなく、大学進学が普通だった。だがその日以後、僕にとって友人達と大学の話をすることは意味のない普通になってしまった。そこに一つの疎外感が生まれた。伝統のある古びた校舎や高く伸びたメタセコイヤのあの三本の木、生徒達のガヤガヤと話す声、グランドの向こうに沈む夕陽、それらのものがなぜか少し遠くに行ってしまったような、自分が少し透明になったような気分になっていった。退屈な授業は益々縁のないものに思われた。
しばらくして担任の進路に関する個人面談が行われた。僕が大学進学を諦めると伝えると、諦めなくていい公務員になって夜間大学へ行く道があると教えてくれた。それは僕にとって天啓だった。すぐに公務員試験を受けて合格した。しかし、当時の国公立夜間大学は難しく合格できなかった。担任は働きながら受験すればいいと励ましてくれた。就職してみると、様々な付き合いが生じ受験勉強は捗らず、ついに二浪になってしまった。とても疲れていた。もう無理だと諦めようとしていた時、雑誌で芥川龍之介が学生の頃、英文で長編の『ジャン・クリストフ』を一週間で読んだと知った。なぜか強く惹かれて自分も挑戦したくなった。もちろん日本語だが。岩波文庫八冊。そんな本を読むのは初めてだった。そこには貧しい音楽家の家に生まれたクリストフが自らの人生を音楽に魅せられながら、困難を乗り越えて成長し、ついに一つの境地に達するまでが流れるような文章で描かれていた。読み終ると何か呆然として、大きなメッセージを受け取った気がした。僕は進まなければいけない、それも何か、ただ受験ということではなく精神的な意味で前に進むんだと決めた。それからは悩まず真っ直ぐな気持ちで勉強を開始した。そして次の春。合格通知を手にした。嬉しかった。だから僕は今でもロマン・ロランを尊敬している。