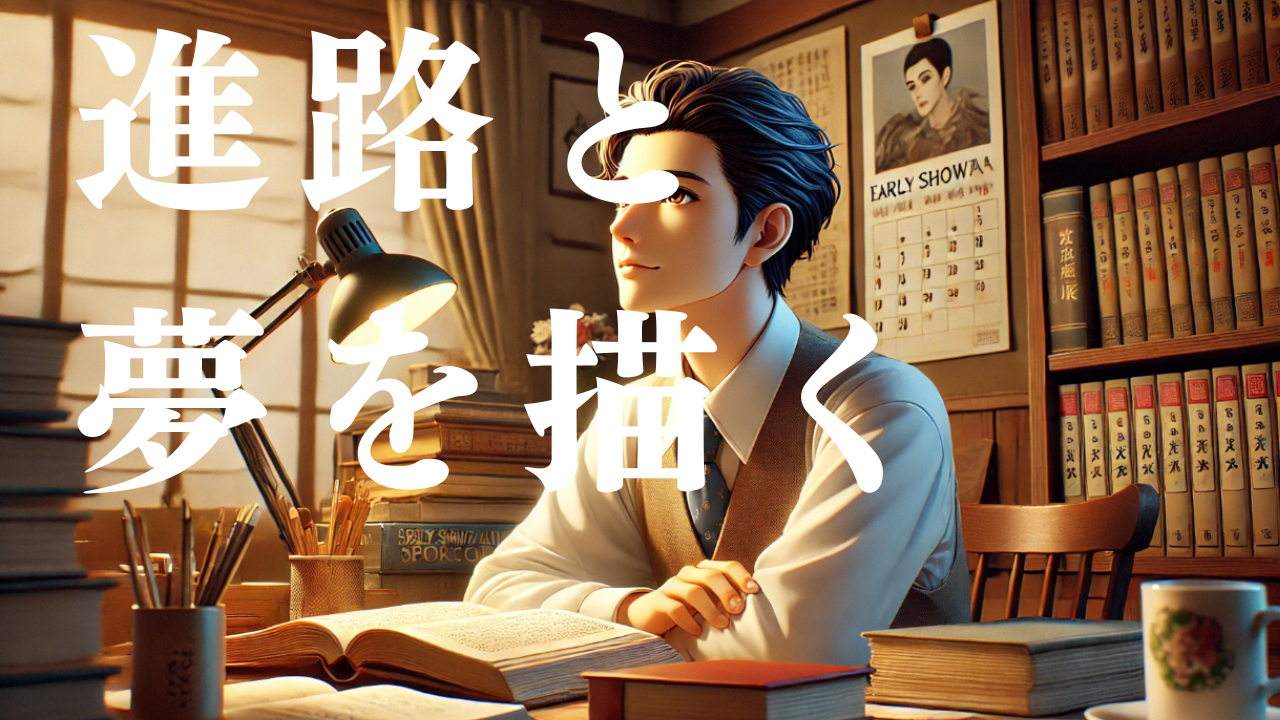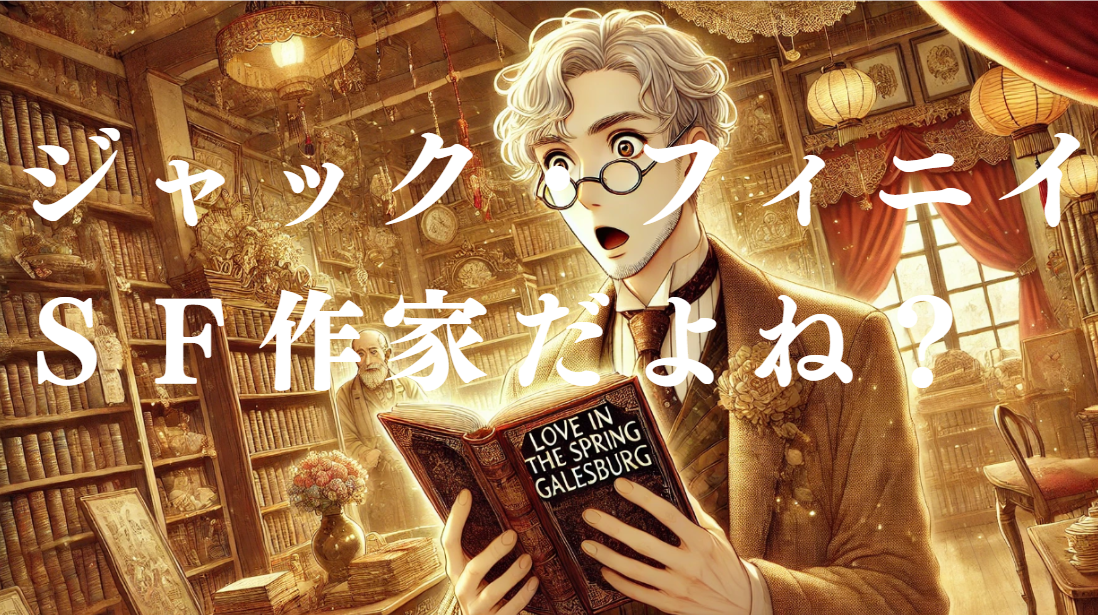たとえばの話
かつて比喩という表現を深く考えたことはありませんでした。普段の会話の中では、物事を例える必要性を感じることがほとんどなかったからです。
就職して、ある企業の総務部に配属された私の初業務は社内報の発行担当でした。それは上司と私、同期の女性の三名で構成されていたのです。
そこで文章に対する視野が一変しました。
当時の上司は、厳格な元新聞記者のようにたかだか社内報記事にうるさかったのです。会社の規模も小さく、社内報の発刊は季刊誌程度だったにもかかわらずです。
上司の教えは洞察に満ち、思考を文章に落とし込む技術がありました。私と同僚に課された練習課題は、時事を題材にした四〇〇字詰め原稿用紙二枚のエッセイ風記事だったことを覚えています。読書感想文さえまともに書けなかった私には、それがまるで遠く険しい山を見上げるような挑戦でした。
当然のことながら、提出した原稿は赤い校正で覆われていました。しかも点数がつけられています。
十七点。
この評価は、スキーでいえばボーゲンどころか斜面に対して板のエッジを適切に立てられるかぐらいの初心者です。新入社員だった私には、ビジネス文書と創作文書の違いもわかりませんでした。
しかし、一筋の希望の光はありました。それは、もうひとりの社内報担当者である同僚、彼女の存在でした。彼女はスマートに原稿を受け取り、自信に満ちた様子で席に戻りました。
ニュース記事っぽくはないけれど、エッセイとしは独創的で面白いという評価で、上司も珍しく褒めたのです。
彼女の原稿には何か特別なものがあると直感しました。
理由は忘れましたが、上司が出席できなかった何度目かの打合せのとき、私は彼女にお願いしました。彼女は軽く微笑みながら、自分の原稿を渡してくれました。
その文体は明快でありながら、個性的で洗練された魅力を持っています。彼女の文章には、読者を一瞬で引き込む魔法のような力がありました。比喩を巧みに使い、言葉に新たな命を吹き込んでいます。
例えの使い方に私は感心したのです。彼女は特に比喩を意識していると答えました。
それが「メタファー」でした。メタファーという言葉自体、初めて耳にしたような気がします。その言葉が、のちの私の読書遍歴に影響を与えました。
次第に彼女と親しくなり、彼女の文才の秘密を知りたいと思い始めたのは自然の流れでした。暑い夏の打合せ後、彼女から村上春樹の新刊が出ることを聞きました。
むらかみはるき? 私は村上春樹の名前は知っていましたが、彼の作品を読んだことはなかったのです。
それが『海辺のカフカ』でした。そのタイトルは私の好奇心を駆り立てました。彼女に影響されて、私は村上春樹の作品を手に取り、読み始めたのです。
不条理の象徴であるカフカ、そして波の寄せる海辺。村上春樹の世界観は、現実と幻想の境界をぼかし、読者を独特の世界へと連れていってくれます。私は比喩の力を信じるようになり、ペンは止まることなく、社内報と向き合うことになりました。
が、上司からは不評でした。社内報に突飛な創作性は必要なかったからです。やはり、無機質な事実を並べる文章を求められました。
それでも彼女と『海辺のカフカ』の出会いに感謝しています。数年後、私はその会社を退職しましたが、社内報の思い出は鮮明に記憶されています。
それは、比喩という素晴らしい技術に心を奪われた記憶の断片です。