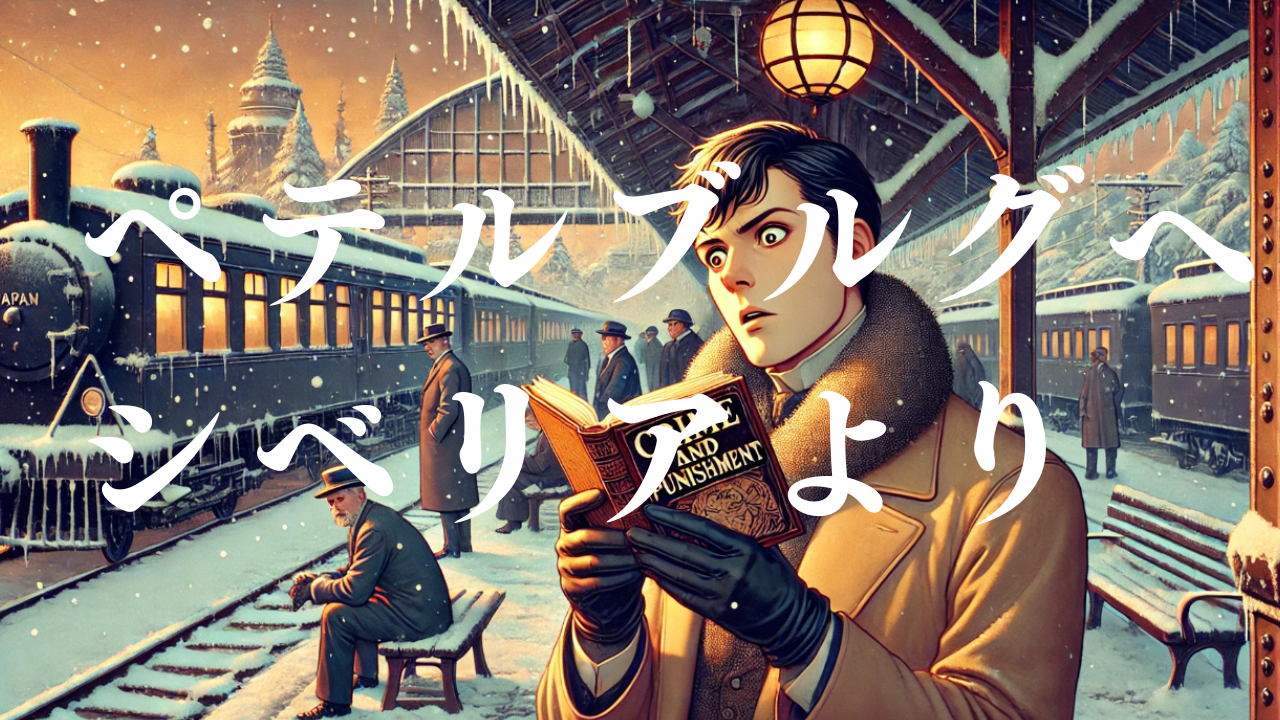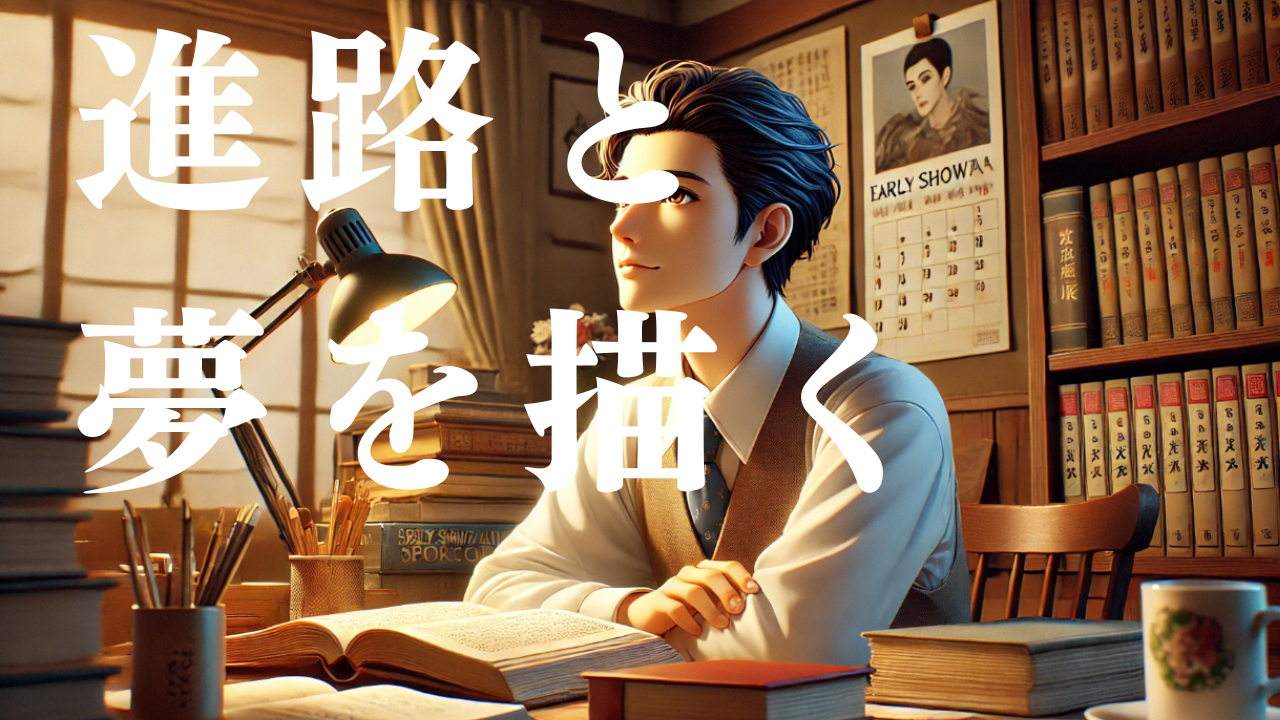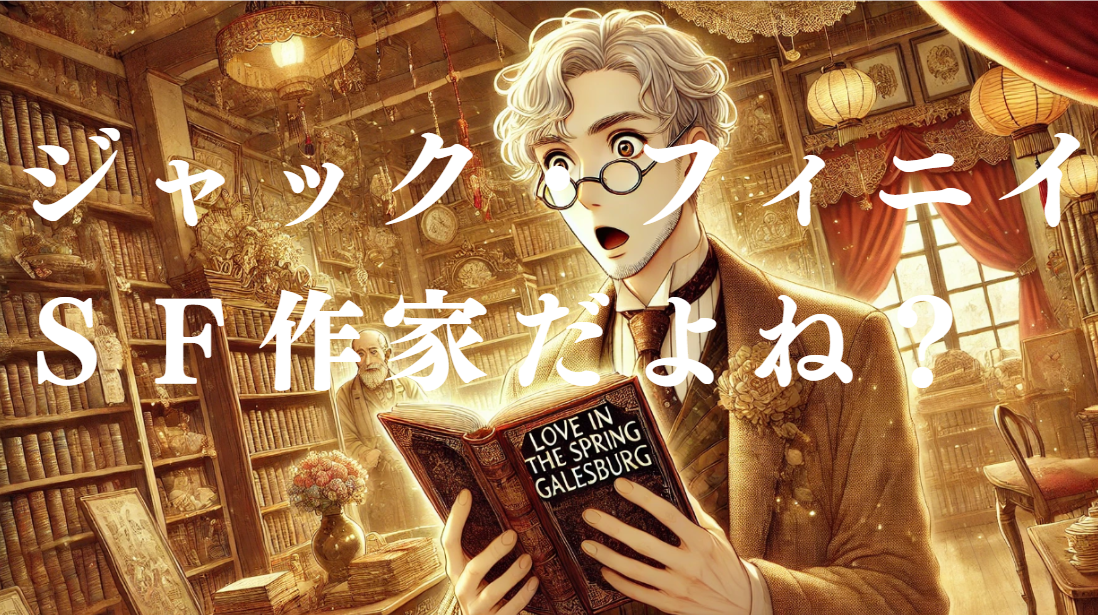ペテルブルグへ、シベリアより
白昼の光以上につよく心を打つ薄明のなかで、彼岸に対する自分のさまざまな期待とたたかう人間の闘争を、ぼくらが捉えることのできる作品が、ここにあるのだ。(A・カミュ『シーシュポスの神話』)
真冬の駅。季節に似合わず黒く日に焼けた少年に目が留まる。みるからに内気がちなその少年は、コードタイプのイヤホンを耳に着け、単語帳だろうか、頁の一部を隠す白い紙切れを上下にそして頁から頁へと動かしながら凝視しては、口の内側で声にならない声で何かを呟いている。彼は毎朝わたしと同じ駅で電車に乗り、わたしよりも一駅早く降りていく。彼はおそらく絶望を知らない、「絶望的に自己自身であろうと欲しないことないし絶望的に自己自身であろうと欲する」というあの絶望をだ。そしてその知らないということさえもがすでに絶望であることには気付こうはずもない。きっと彼はこう固く信じているに違いない、電車が彼を運ぶように外を流れる時間が彼を目的地へ連れて行き、その目的地自体は自分の努力次第でどことでも選べるのだ、と。そんな彼にとって「問題」とは、常に「答え」が用意されているものなのだ。だから、どんなに複雑奇怪に捻れた数式であろうと、明確に切り取られた端部から辿っていくことになんの躊躇いもなかった、いやむしろその戯画的な一本の筋を掴んでいることに喜びさえ感じていたのだ。
* * *
ドストエフスキーは十代のうちに読まなければ読んだことにならない、とある小説家が述べていた。曰く、二十歳を過ぎてはドストエフスキーの毒は全身に回らない、とのことだ。ということは、わたしが感じたあの痺れはどうやら本物ではないらしい。わたしはその毒を浴びるのにあまりにも遅すぎたようだ。わたしはあまり自身の過去に執着したくはない、それは常に決別していくべきものだからだ。しかし、わたしがわたしの過去において後悔していることがあるとすれば、それは高校時代に全く本を読まなかったことである。
さて、そんな少年の未来はどんなものだろうか、とわたしは想像する。答えのある問題に安住する少年は、いずれ石の壁の内に閉じこもるにちがいない。そう、あの地下室人が打ち破ること叶わず呪詛した二二が四の石の壁だ。「そういう石の壁がほんとうに安らぎであり、ほんとうにそこに平和の保証めいたものが含まれてでもいるようではないか。」地下室人は叫ぶのだが少年の耳には届かない。その内側は空想的なユートピアである。そこでは自然法則が絶対的な権威を持ち一切を支配している。全ての物体はその権威を借りて、面倒な条件を離れ、理想的な形状を与えられている。対称的に広がる過去と未来の時間軸上でそれらは永遠の運動を手に入れるのだ。ここでは何もかもが彼の想像どおりに展開する。そして彼はこの括弧付きの全能感にひたりきり、ついにはそれが本物であるかの如く錯覚するようになる。「神はない、従って自分が神だ。」福永武彦が描いた青年は、自らが運命であることを称し己の生命さえもその手で支配したのだが、全能の錯覚が孕むのはこれと全く相似形の危うさである。或いはまた次のような場合を想像する、つまりその少年が運良く壁外へ出られた場合である。運良く、とは言ってもそれはほとんど必然の出来事である。なぜなら彼はいずれ科学者か労働者かを選択し否が応にも社会へ参入させられるのだから。問題はそのとき彼が抱く思いである。他者と可能性という未知の大波を前に、かつて彼を守った穏やかな空想がなんの防波にもならないことを知ったときの思いである。彼にとってはそれらが己を蝕むように思えてならないだろう。そして無益にも黒塗りの一家の次男のように「そんな入場料を払うのはまるで僕らの懐ろに合わないよ」などと叫んでどうにもならない現実という神に対して反逆を試みるのかもしれない。
* * *
少年の降りる駅の到着が近づく。「たとえ可能な科学の問いがすべて答えられたとしても、生の問題は依然としてまったく手つかずのまま残されるだろう」わたしはひと息に哲学書の一文を呑み込み、そして息継ぎとともに少年の様子を伺う。彼は相変わらず単語帳と格闘している。わたしは知っている、この哲学者の探求が、アイスバーンの滑落から摩擦ある地面へ回帰したことを。この少年に必要なのもまさに同じ転回なのだ。だからこれはわたしの役目である、彼に未来を生きる言葉を届けることは。君は今日も右に左に引き裂かれそうになりながら生活を続けるだろう。しかしそれでよい、歴史を生き、様々な感情があるのを知ることだ。いま電車を降りようとする君に伝えたい。ラスコーリニコフの物語を、『罪と罰』という物語を。