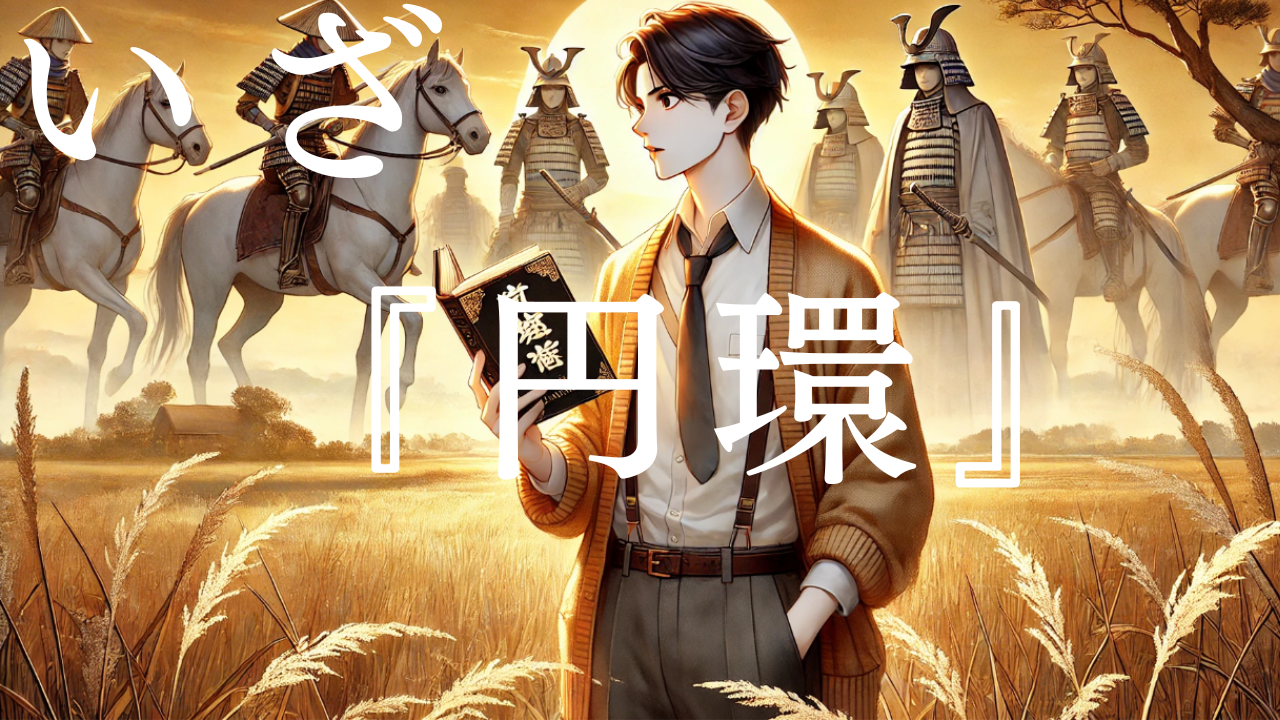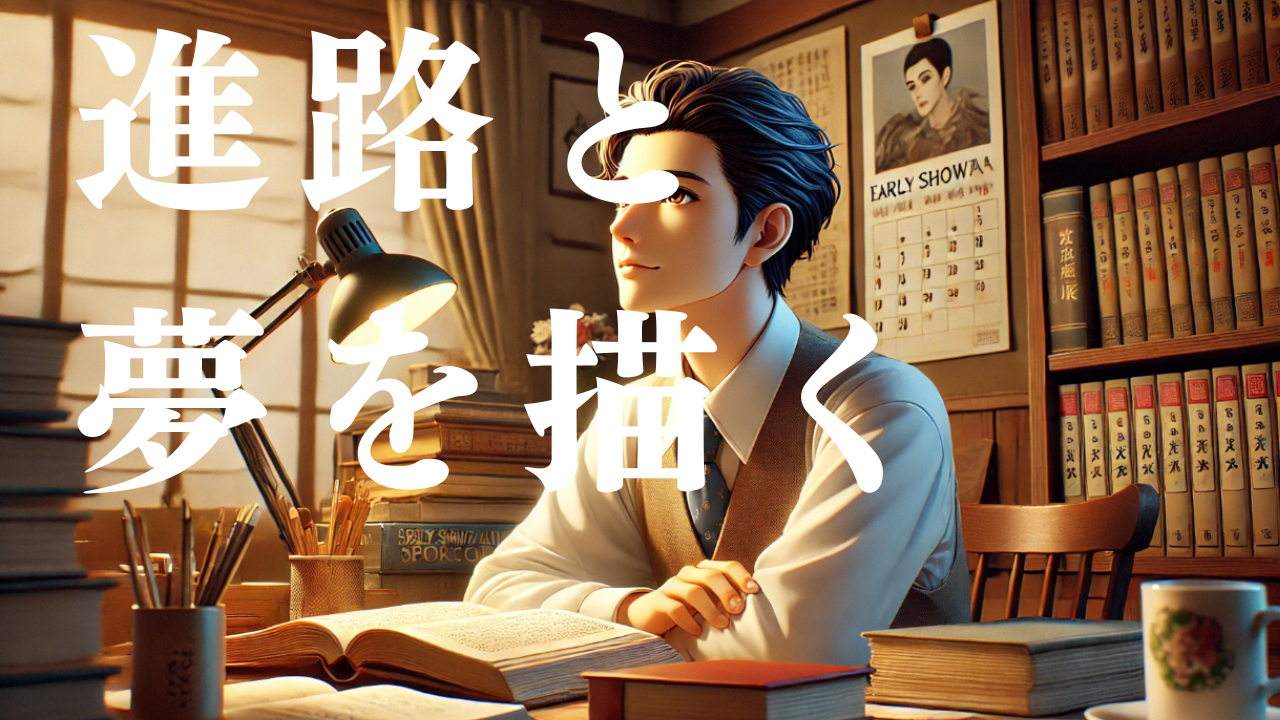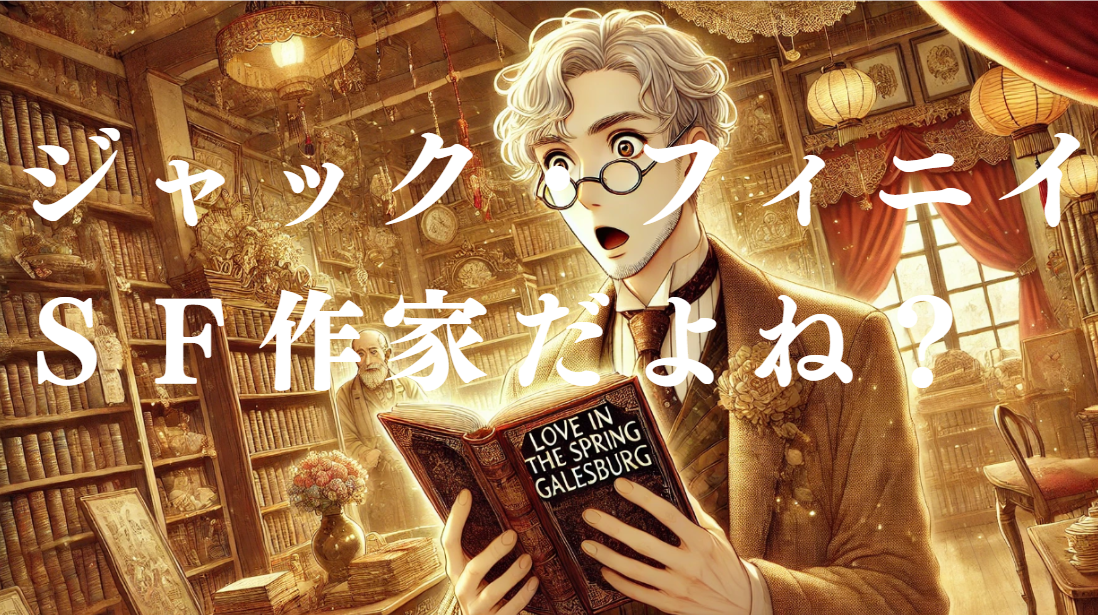いざ『炎環』
2023年1月に97才で亡くなられた永井路子さんの『炎環』(1964年)は、平安時代末期から鎌倉時代初期、源頼朝を旗頭とした東国武士の挙兵から武家政権樹立、そして政権を確たるものにした承久の乱まで、貴族の世から武士の世へ移り変わる時代を舞台とした4つの物語から成る歴史小説です。この四編では同じような状況が異なる主人公で描かれ、作者はあとがきで「それぞれ長編の一章でもなく、独立した短編でもなく、一人一人が主役のつもりでひしめきあい傷つけあううちに、いつの間にか流れが変えられてゆく——そうした歴史というものを描くための一つの試み」と記しています。
四編のうち「悪禅師」「黒雪賦」「いもうと」では、それぞれの主人公(阿野全成(頼朝の弟)、梶原景時(頼朝の重臣)、北条保子(阿波局 北条政子の妹))が、秘めた情念や野望を別の力に阻まれ失意に沈んでいく姿を、最後の一編「覇樹」では、伊豆の青年小四郎が鎌倉幕府の権力者北条義時へ変貌していく姿を描いており、落ち着いた文章ながら内容は題名の通り熱く、全編で330ページほどですが、非常に読み応えがあります。
私はこの小説が本当に好きで、これまで読んだあらゆる小説の中から一つ選べと言われれば、迷わずこの作品を選びます。初めて読書会に参加した時の初紹介本には当然『炎環』を選びましたし、過去に参加した読書会でも必ず紹介しています。
鎌倉時代初期と言えば、三谷幸喜脚本の『鎌倉殿の13人』(2022年NHK大河ドラマ)が大きな反響をよびましたが、1979年の大河ドラマでも『草燃える』という、同じ時代を描いた作品があり、このドラマが原作の一つである『炎環』と出会うきっかけとなりました。
『草燃える』では、石坂浩二(源頼朝)、岩下志麻(北条政子)、松平健(北条義時)をはじめとする名優たちが、ある時は団結して敵に立ち向かい、ある時は互いに抗争する武士たちと取り巻く人々を熱演し、人が力と知恵の限りを尽くして戦うこれほどの激しい歴史があったのかと、当時高校生だった私は食い入るように見ていました。
実際には、ドラマ放映後から幾年か経過して『炎環』を読み始めましたが、ドラマの印象が強かったため、初めて読んだ時には「これがあの『草燃える』の原作か」と感嘆し、その後数えきれないくらい読み返し、登場人物のセリフの一部を覚えたほどです。さらに文庫の新装版が出た時には迷わず買い替え、新装丁版や電子書籍版も購入し、『炎環』以外の永井路子作品も数多く読みました。
本であれ、映画であれ、ドラマであれ、多感な10代20代に嵌った作品は強く印象に残り、その後の好みのジャンルや考え方に影響を及ぼします。私の場合『草燃える』を含む大河ドラマ作品から影響を受け、日本史そして歴史全般に興味を抱くようになりました。
最後に、この文章で興味をもたれた方には是非『炎環』を読んでいただきたい。何巻にも及ぶ長大な作品ではないので、手に取りやすいはずです。戦国時代と比べてなじみの薄い人物が多く登場しますが、構わず読むか、調べながら読むか、『鎌倉殿の13人』の配役をイメージして読むか、いずれでも結構です。読んだ後には新しい世界が広がっていくことでしょう。