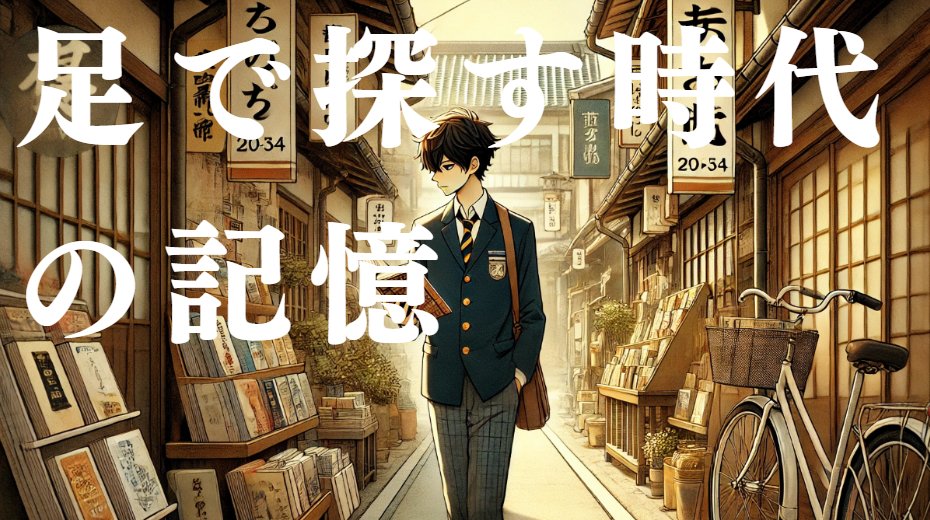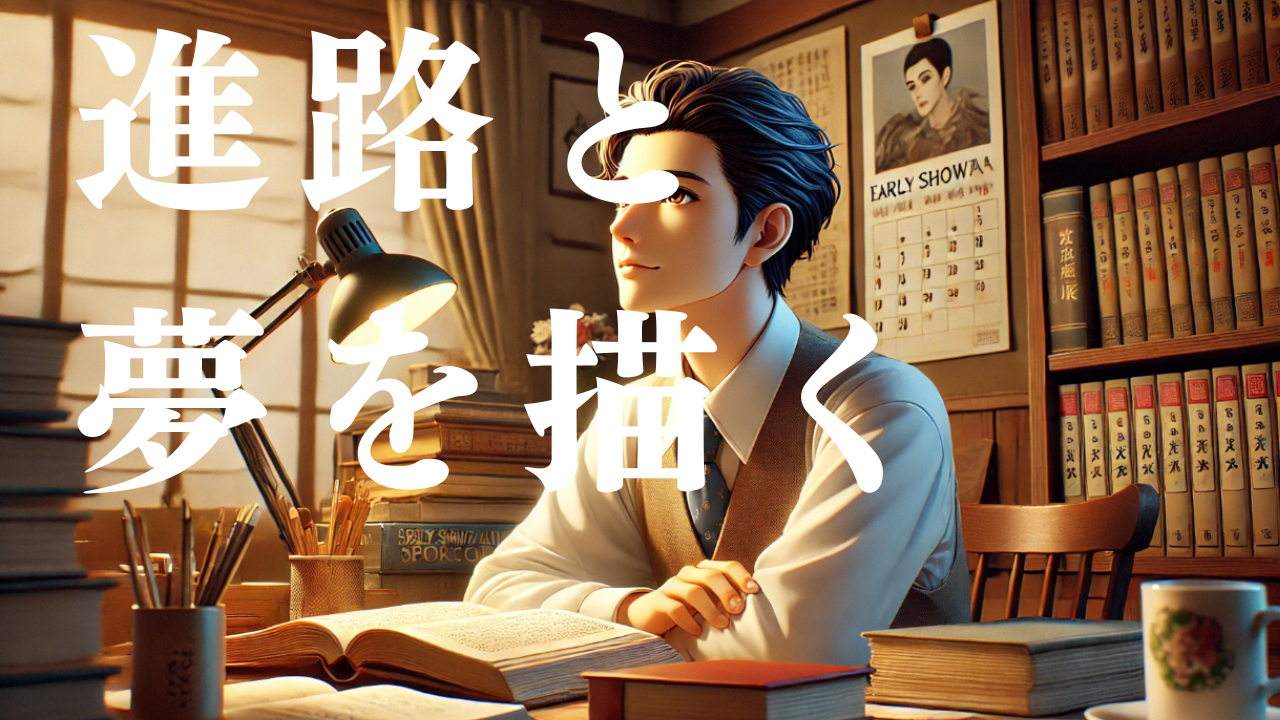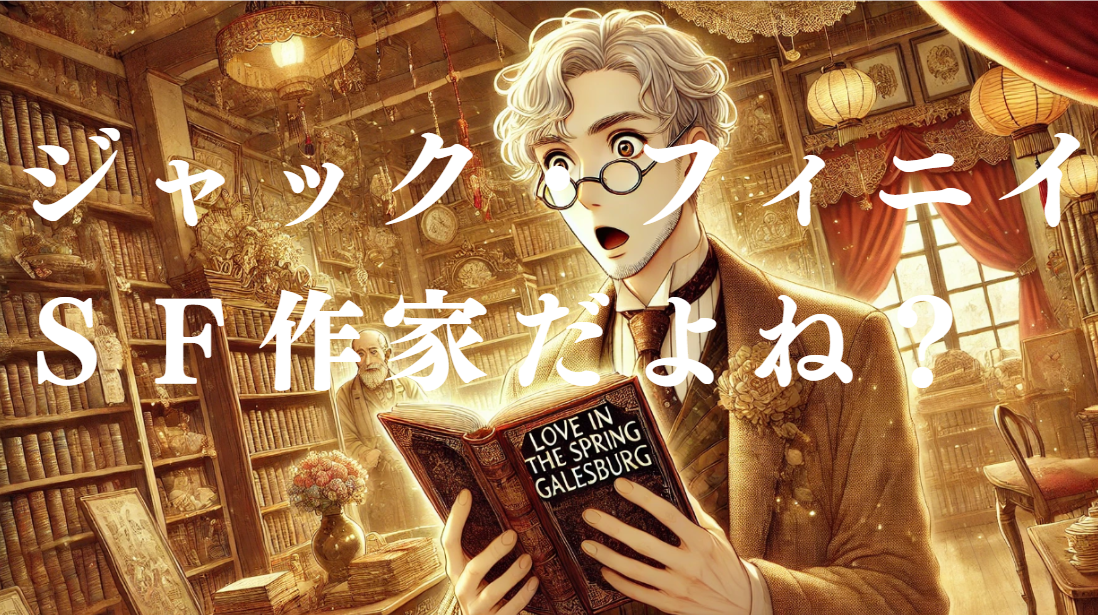足で探す時代の記憶
私が高校生の頃は、現在のように大型書店というものが地元にはない時代でした。本屋さんも近くの商店街に一つあるだけで、自転車で二〇分か三〇分走って一軒、また二〇分くらい走ってまた一軒と、本屋さんというものが宝物のように輝いていた時代でした。本屋さんによって品揃えが変わっていて、見つける本も本屋さんで違うので本選びがとても楽しい時代でした。
当時、本だけでなく香港映画にも嵌っていました。好きな映画の原案がどうしても気になって、必死になって探したことがあります。エンドクレジットで作家の名前を見つけてそれをメモして本屋を巡りました。地元では見つからず、神戸三宮や梅田の大型書店にあることを期待してそれぞれ行きました。インターネットの普及がない時代、本も足で探す時代でした。結局見つけられず、店員さんに聞いても作家金庸の作品はないとのことで、意気消沈しました。それから何年経ったでしょう。七、八年でしたか。金庸の名前を新聞の広告で見つけた時に衝撃を受けました。初の日本語訳刊行ということで、メディアに取り上げられたようです。金庸の一作目、その名も「書剣恩仇録」。武俠小説という、日本の時代小説とは異なる新しいジャンルの小説で、どんな内容なのだろうと、発売日にわくわくして街の本屋さんに行きました。手にした時は胸が踊りました。その日一日、夜通し読みました。内容も面白かった上、以前見た映画の原作ではないのですが、それを彷彿とさせる内容でした。中華人民十億人が読んでいると謳われる大作家、金庸。金学と言われる金庸作品を研究される学問まで存在し、作品全てが中華圏で映像化されています。
その後、私が高校生の時に探し求めていた映像作品の原作も遂に刊行。手にした時は喜びに震えました。今でも私の宝物です。記憶に残る本との出会いですね。